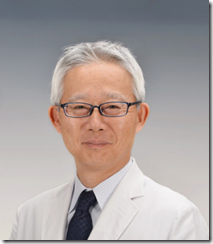泌尿器科の名医で医学博士の堀江重郎(ほりえしげお)先生は「100年もの間、元気な腎臓と膀胱を作ろう」と呼びかけ、尿活トレーニングを提唱している。
「夜3回以上トイレに起きる人は、そうでない人に比べて死亡率は2倍にもなる」と、日ごろあまり関心をもたれない膀胱や尿に関して、注意を呼び掛けている。
夜3回以上トイレに起きる人は何と死亡率が2倍に
堀江重郎医師は泌尿器科のエキスパートで医学博士。東京大学医学部を卒業後、日米の医師免許を取得し、米国で腎臓学の研鑽を積んだ後に帰国。2003年に帝京大学医学部主任教授就任後、2012年から順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学主任教授に就任し、現在は腎臓病・ロボット手術の世界的リーダーである。特に科学的なアンチエイジングには詳しく、日本抗加齢医学会理事長、日本Men’s Health 医学会理事長としても大活躍している。
堀江先生によると、「夜中や日中にしょっちゅうトイレに行きたくなる症状は、実は寿命が縮まるサインです」と言う。夜中に1回以上排尿のために起きる症状を夜間頻尿、日中に8回以上トイレに行く症状を頻尿というが、どちらもしょっちゅうトイレに行きたくなる症状だ。この症状は実は高血圧、動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病と密接に関わっていると、堀江先生は指摘している。
高血圧は心臓に負担をかけ、動脈硬化を引き起こす。さらに、動脈硬化が進むと脳梗塞や心筋梗塞のリスクは一気に高まる。さらに糖尿病は失明につながりかねない網膜症や、手足のしびれや壊疽を引き起こす神経障害、重度の腎障害を引き起こす。なかでも慢性腎臓病は日本人に多い国民病ともいわれ、患者数は増加している。しょっちゅうトイレに行きたくなるという症状の裏にはこうした恐ろしい病気が潜んでいる可能性があると、堀江先生は注意を呼び掛けている。
「夜3回以上トイレに起きるひとは、何と死亡率がそうでない人の2倍になるとも言われています。頻尿が起こり始めた時に、膀胱や腎臓だけに動脈硬化や血流悪化が起きているとは考えにくいでしょう。つまり、夜間頻尿や頻尿は全身の血管が固くなって詰まっていることを、物語っているのです」と、新刊書「尿で寿命は決まる 泌尿器の名医が教える 腎臓・膀胱 最高の強化法」(SBクリエイティブ刊、定価1540円)で、尿の異常が身体の異常を警告していると言う。
「しょっちゅうトイレに行きたくなるだけではなく、トイレが間に合わないことがあるという人も少なくありません。研究機関の調査では50~70歳代の男性の3割に尿漏れの症状があるという結果が出ています。年齢のせいとあきらめるのではなく、もっと尿に関心をもって接し、尿トレなどで元気な尿を取り戻してください」としている。
オフィスでできる3つの尿トレ方法
頻尿や尿失禁、排尿困難、残尿感の一因は膀胱の筋肉が柔軟性を失ったり衰えたりして起きる。そのため、堀江先生は効果的な「尿活トレーニング」を提唱している。今回はビジネスパーソンがオフィスでもできる、簡単で効果のある3つのトレーニングを紹介しよう。
その1)座ったまま肛門エクササイズ
膀胱は身体の背面、お尻の近くにあるため、肛門エクササイズは間接的に膀胱の筋肉までストレッチされ、膀胱の血行が良くなり、膀胱の柔軟性が復活する。
やり方)
イスに座って足を肩幅に開いて足裏を床につけるようにする
肛門周りの筋肉を締める
(締める時間は最初は5秒ぐらい。5秒力を入れて緩める、を繰り返して10回を目安に行う)
力の入れ方が感覚でわかるようになったら、男性は尿道や陰部全体を引き上げるイメージで力を入れることがポイント。また、ぎゅっと締める時間は5秒から少しずつ増やしてもよい。男性の「ちょい漏れ」に効果がある。
その2)トイレに行ったら尿道エクササイズ
トイレを我慢すると膀胱の筋肉が自然にストレッチされる。トイレに行くことを我慢しすぎるのは、膀胱炎の原因となるので、日常生活で普通にトイレに行った時にやることがポイント。
やり方)
トイレに入って排尿をする直前に、3から5秒間、尿を出すのを意識的に止めて我慢する
男性だけでなく女性にも効果がある方法だが、あくまでも「トイレに行くこと自体を我慢する」のではなく、尿を出そうとする前に止めて我慢すること。
その3)快尿エクササイズ、スクワット
下半身の筋肉を鍛えることで膀胱だけでなく、前立腺肥大の予防にも効果的。エクササイズは正しい姿勢で行うことが重要で、肛門を引き締めながらお尻を後ろに引いて、かかとに体重を乗せるようにする。膝が内側や外側に向かないことがポイントで、膝の向きと人差し指の向きを揃えると上手く行く。
やり方)
まずは足を肩幅に広げ、安定感があるイスを使って「座る、立ち上がる」を繰り返す。こうして正しいスクワットの動きを身に付けることができたら、イスの背もたれをもってスクワットをする。
スクワットの姿勢を身に付けるために、イスに「座ったり立ったり」を繰り返す時、まっすぐイスに座るのではなくお尻を後ろに引くようにしながら座るのがポイント。慣れてきたらイスを使わずにできるようになる。一日10回が目安。
これらの運動は堀江先生が監修したキッセイ薬品工業の「尿活トレーニング~笑顔でスッキリ~おしっこ新ライフ」でエクササイズの動画がアップされているのでぜひ参考にしたい。新刊書では上記3つの他にも骨盤底筋体操、プランクなど尿活に効果があるエクササイズも紹介されている。
こうした運動は単に尿活に役立つだけでなく、血管をさび付かせないためのトレーニングでもある。堀江先生によると、男性では42歳が血管年齢の曲がり角であり、42歳になるとそろそろ血管がさび付いてくる傾向にあると教えてくれた。最近は血管年齢という言葉が流行っているが、いかに血管の細胞をさび付かせないかが長寿の秘訣である。尿が教えてくれる血管の衰えを自覚したら、ぜひ堀江先生の尿活トレーニングを始めよう。
堀江重郎先生
泌尿器科医、医学博士。1960年生まれ。東京大学医学部卒業。日米の医師免許を取得し、米国で腎臓学の研鑽を積む。2003年帝京大学医学部主任教授、2012年より順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学主任教授。腎臓病・ロボット手術の世界的リーダーであり、科学的なアンチエイジングに詳しい。日本抗加齢医学会理事長、日本Men’s Health 医学会理事長。新刊書「尿で寿命は決まる 泌尿器の名医が教える 腎臓・膀胱 最高の強化法」(SBクリエイティブ発刊、定価1540円)
キッセイ薬品工業
尿活トレーニング~笑顔でスッキリ~おしっこ新ライフ
文/柿川鮎子
「夜間頻尿」の予防法はご存じですか? 日常生活で取り入れたいセルフケアも医師が解説!

「夜間頻尿」の予防はご存じですか? 生活習慣で改善できることもあるそうです。今回は、すぐに実践できる夜間頻尿のセルフケア方法について「港南台かわかみ泌尿器科クリニック」の川上先生に解説していただきました。
※この記事はMedical DOCにて【「夜だけ頻尿で目が覚める…」医師が夜間頻尿の原因や治し方・セルフケア方法を解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

監修医師:
川上 稔史(港南台かわかみ泌尿器科クリニック)
プロフィールをもっと見る
![]() 編集部
編集部
夜間頻尿対策のセルフケアを教えてください。
![]() 川上先生
川上先生
すぐに実践できることとしては、たくさん尿が出ている人は「寝る前に水分やアルコールを控えること」「夕方以降はカフェインの摂取を控えること」などでしょうか。それから、運動不足やストレスも夜間頻尿の原因になりますので、気をつけるようにしましょう。
![]() 編集部
編集部
運動不足も夜間頻尿と関係あるのでしょうか?
![]() 川上先生
川上先生
はい。運動不足になると下肢の血流が悪くなり、むくみが生じます。つまり、足に水分がたまっているという状態で、この余分な水分はやがて尿になり、夜間頻尿の原因になるのです。解決策として、ウォーキングやふくらはぎを使う運動など、下半身に刺激を与える運動を習慣化するといいでしょう。そして、可能であれば夕方以降に運動することがおすすめです。あるいは、昼間のうちに足を上げておくなど、夕方以降に足がむくまないような工夫も効果的です。
![]() 編集部
編集部
食事面で気をつけることはありますか?
![]() 川上先生
川上先生
「塩分の摂り過ぎ」には要注意です。塩分をたくさん摂ると体外へ排出しようと尿量が増えてしまいます。とくに高血圧の治療されている人は、厳格な制限が必要です。また、就寝の2時間くらい前からできる限り水分摂取を控えるのも夜間頻尿対策になります。
![]() 編集部
編集部
あらためて、夜間頻尿とどのように向き合えばいいのでしょうか?
![]() 川上先生
川上先生
夜間頻尿はQOLを低下させる困窮度の高い症状です。もし、日常生活に支障が出ているのであれば、ぜひ泌尿器科を受診してください。もしかしたら、夜間頻尿の背後は、心不全、糖尿病、高血圧などの生活習慣病が隠れているかもしれません。そうした疾患を見つけたり、生活習慣を見直したりするキッカケになります。規則正しい生活へ改善する一助にもなるでしょうから、もし生活に支障があれば一度受診していただきたいと思います。